全国の学校での講演や授業の記録

千葉県立佐原高等学校にて講演

兵庫県立福崎高等学校にて講演

佐賀県立武雄高等学校の生徒たちにオンライン講演

秋田県立秋田南高等学校にて講演

こども英会話教室 ELS21にて講演

神戸市立上野中学校にて講演

国立大阪教育大学附属天王寺中学校にて講演

山口県立萩高等学校にて講演と授業

KIMUTATSU CHANNEL / キムタツチャンネル /

【人生観】62歳の誕生日に人生を考えた。
478回視聴・ 2026.01.29(木)

【共通テスト】高1生徒と高2生徒に向けて話しました。
729回視聴・ 2026.01.23(金)

【子どもたちの主体性を育成するには】
589回視聴・ 2026.01.15(木)

【共通テスト英語】直前期 勉強法
1,622回視聴・ 2026.01.10(土)

【2026年】キムタツチャンネルを再開します!
913回視聴・ 2026.01.02(金)

【東京大学】学校の合格実績を上げるために
1,508回視聴・ 2025.03.15(土)

【東大英語】2025年東大英語、分析と対策
2,823回視聴・ 2025.03.13(木)

【まるまる反復英文法総復習】本書を作った想いを生徒たちに話しました。
617回視聴・ 2024.11.13(水)
キムタツがお勧めする本のご紹介
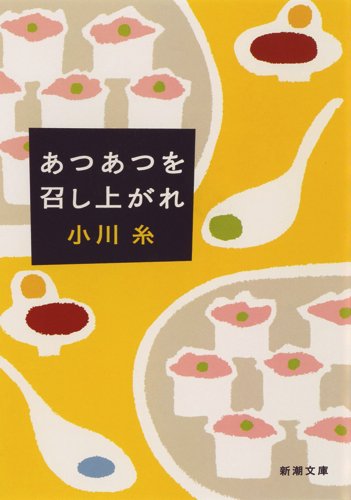
あつあつを召し上がれ
誰にだって忘れられない味がある。身も心も温まる、食卓をめぐる7つの物語。
出版社: 新潮文庫
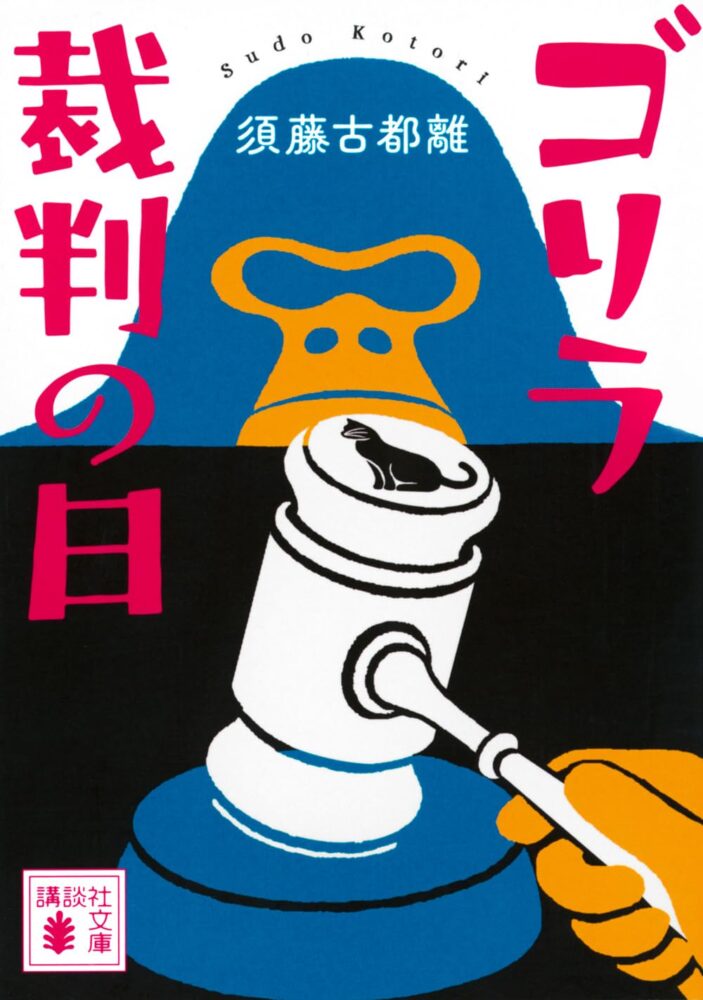
ゴリラ裁判の日
手話が使え、人間に匹敵する知能を持つニシローランドゴリラのローズ。ある事故が起き、彼女は人間と裁判で闘う。
出版社: 講談社
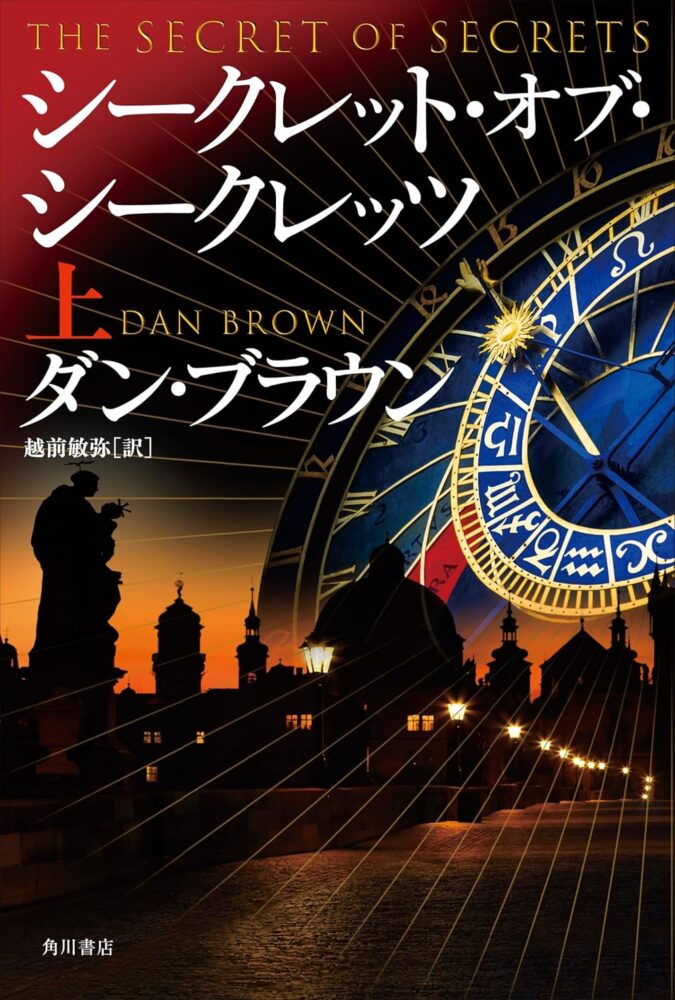
シークレット・オブ・シークレッツ
ダ・ヴィンチ・コード』著者8年ぶり最新刊。ラングドンが帰ってきた!
出版社: 角川書店
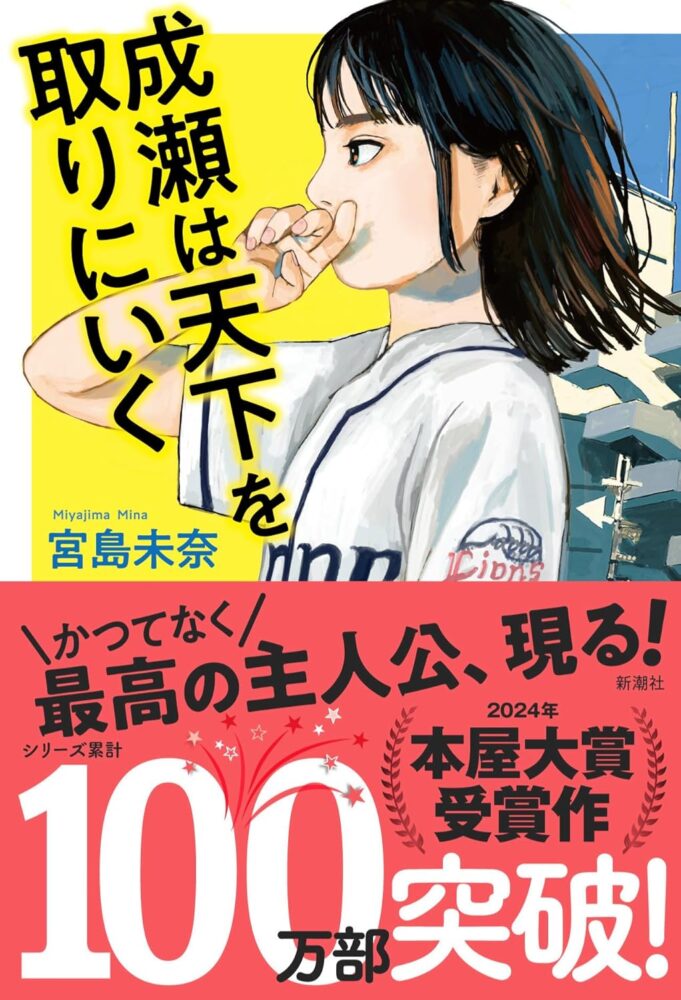
成瀬は天下を取りにいく
成瀬あかりの姿を通して、「自分らしくあること」の大切さを描いた作品
出版社: 新潮社
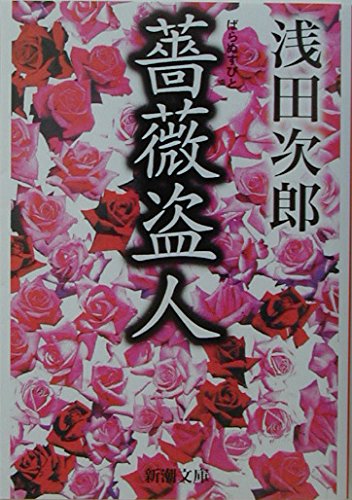
薔薇盗人
人間の哀歓を巧みな筆致で描く、愛と涙の短編小説集。
出版社: 新潮文庫
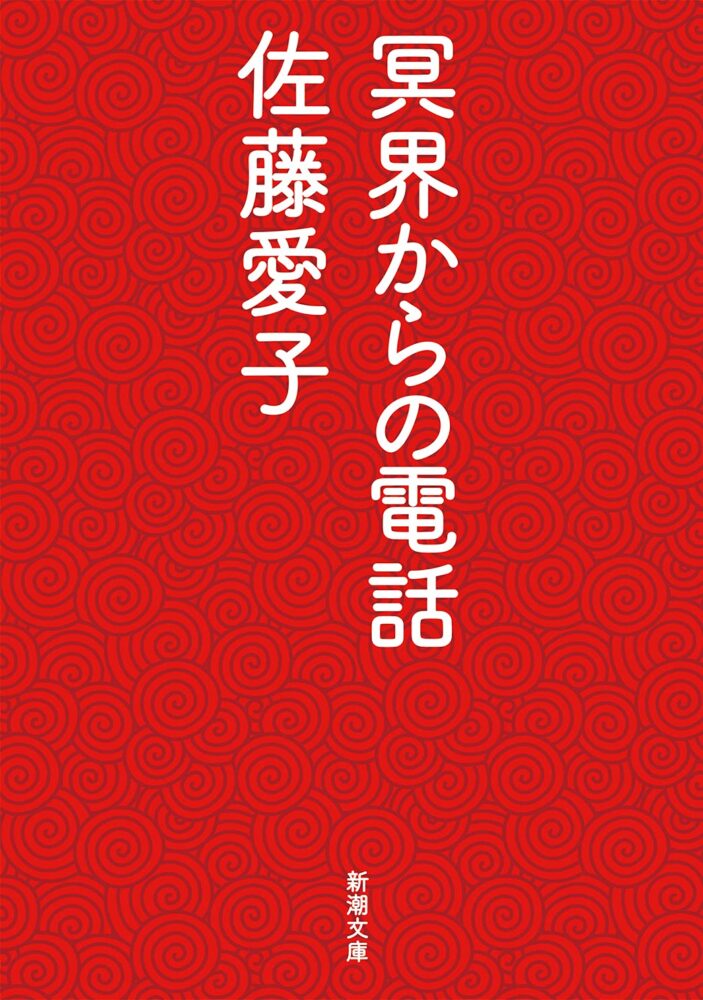
冥界からの電話
ある日、死んだはずの少女から電話がかかってきた。信じられないかもしれませんが、これは本当にあった出来事です。
出版社: 新潮文庫

県庁おもてなし課
高知県の観光を盛り上げるために設立された「おもてなし課」の職員と観光大使の奮闘記。
出版社: 角川書店
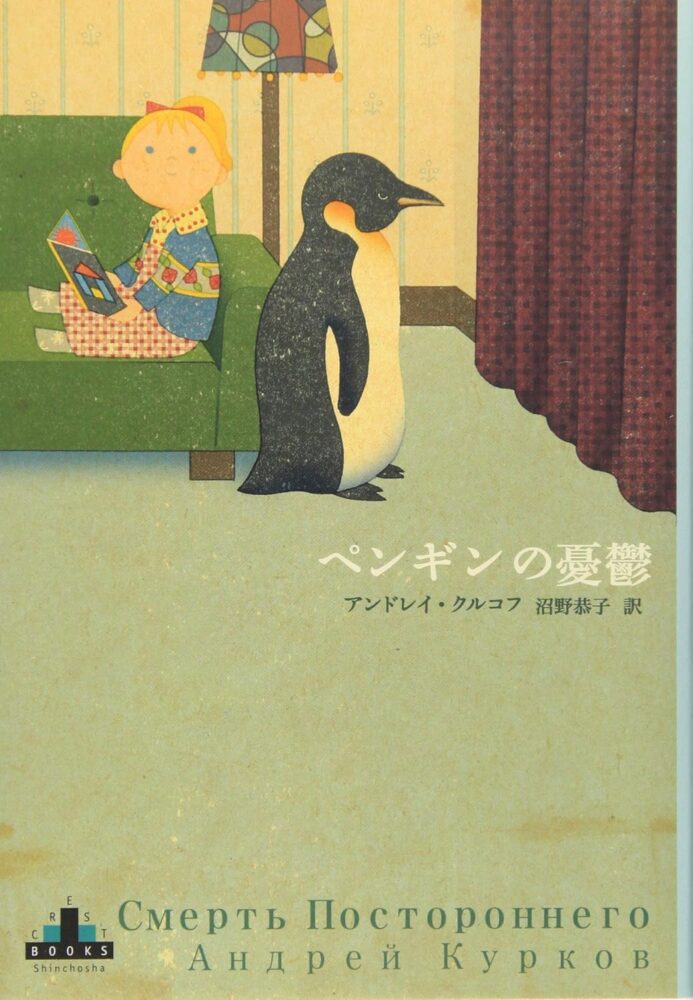
ペンギンの憂鬱
売れない作家ヴィクトルと動物園から引き取ったペンギンとの不思議な暮らし。
出版社: 新潮クレスト・ブックス
キムタツの最新著書一覧
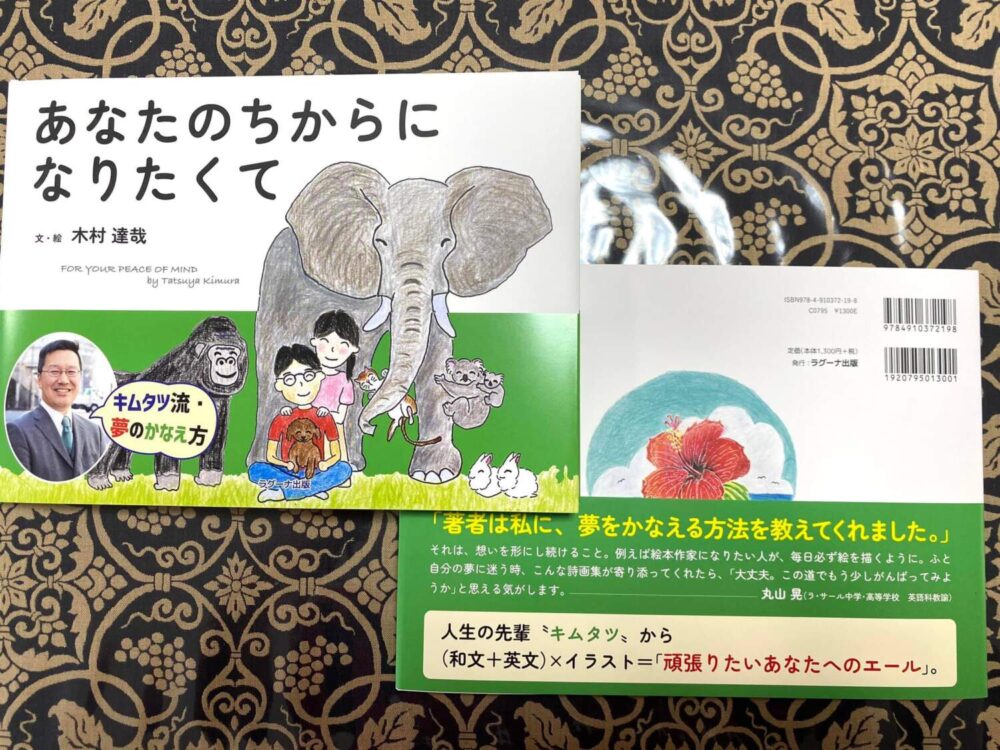
あなたのちからになりたくて
どうしても頑張れないなぁという時もあるでしょう。そんなときに開いてください。
出版社: ラグーナ出版
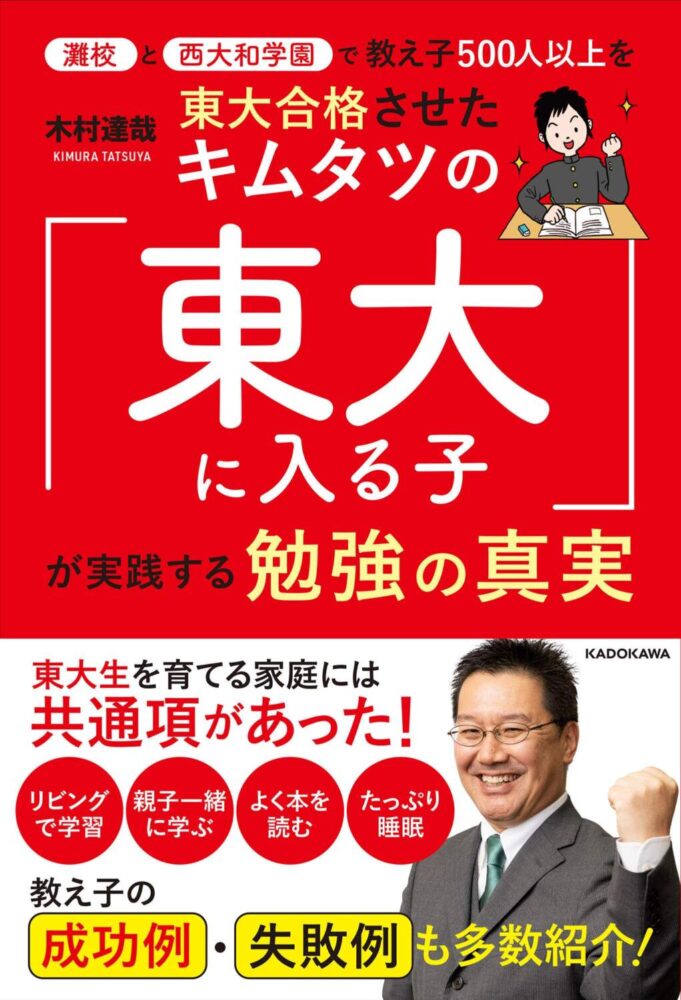
東大に入る子が実践する「勉強の法則」
30年を超える指導経験で分かった、東大合格者を出す家庭の共通点。「勉強体質」を家庭でいかにつくるか。
出版社: KADOKAWA
1650円(税込)

夢をかなえるリスニング ユメリス0 CEFR A1レベル
出版社: アルク
発売日: 2021年03月16日
990円(税込)

夢をかなえるリスニング ユメリス2 CEFR B1レベル
出版社: アルク
発売日: 2021年02月04日
990円(税込)

徹底反復シリーズ 《5-STAGE》 英文法完成 BOOK 3
出版社: 数研出版
発売日: 2021年02月04日
1,382円(税込)
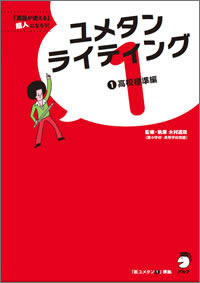
ユメタン ライティング(1) 高校標準編
出版社: アルク
発売日: 2021年02月04日
990円(税込)

ユメタン ライティング(0) 高校入門編
出版社: アルク
発売日: 2021年02月04日
990円(税込)

共通テスト対策リスニング 10分+30分
出版社: 新興出版社啓林館
700円(税込)